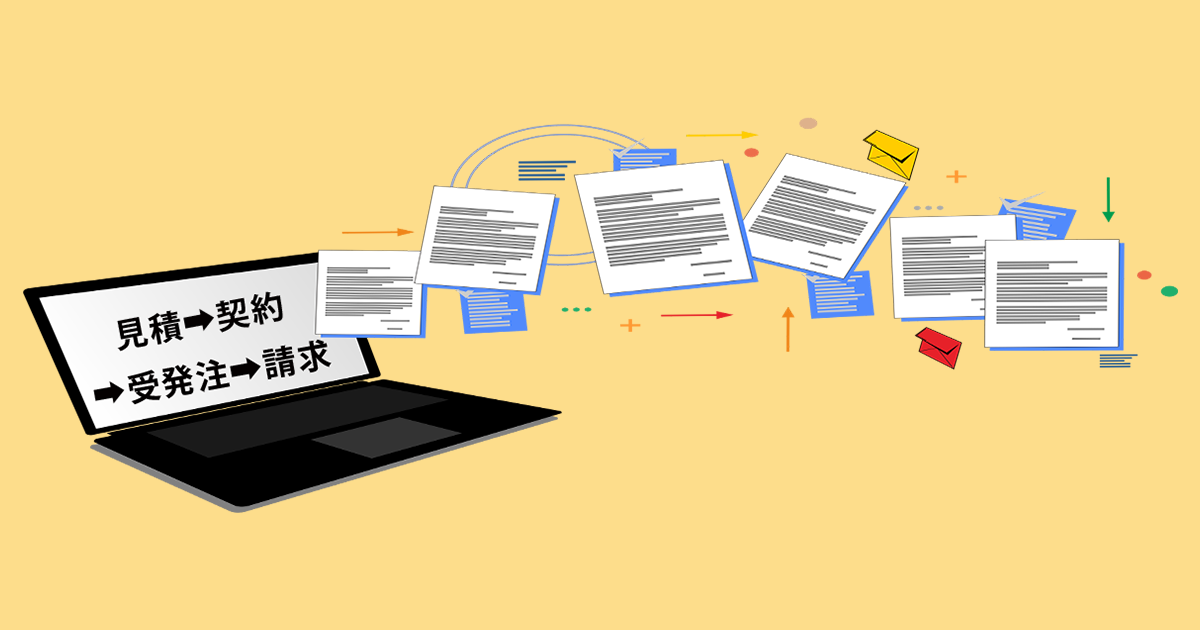昨年、当社が承った請求書DXの資料請求件数は、一昨年の4倍超に上りました。自治体職員の皆様からは「近隣の自治体がシステムの導入を検討しているから」「請求書のDXについて議員から質問を受けたから」といった率直な理由も聞かれ、デジタル化の波に乗り遅れないよう奮闘されている姿が窺えました。自治体における会計事務DXで、請求書のデジタル化が最優先で望まれていることは、自治体へのアンケート結果でも明らかです。帳票類の中で最も取り扱い件数が多い請求書は、デジタル化が進めば、大幅な業務効率化が期待できるからです。しかし、多くの自治体が請求書DXを急ぐ理由は、それだけではありません。
当社は、過去にも請求書をデジタル化する理由をいくつか紹介しましたが、大きくは2つに分類できると思います。今回は、その2つを紹介致します。
インフォマートは自治体と民間事業者双方の業務効率化のために様々な活動をしています。会計事務DXに関することなら、何でもご相談ください。
理由1.業務時間とコストの大幅削減が見込めるから。
一般的に自治体は都度請求のため、請求書の取扱件数は他の帳票類に比べて圧倒的に多くなります。紙の請求書を受け取った場合、請求書の不備確認と不備による差戻し行為、支出負担との照合作業、財務会計システムへの入力、支出命令書の作成と庁内決裁後のファイリングなど、かなりの業務時間を要します。結果として支払遅延のリスクも発生します。請求書DXの方法はいくつかあります。『事業者にとって、デジタルデータ型の請求書が有効である理由』の記事で紹介してますので、こちらの記事も参照ください。
人口15万人規模の自治体で実施した実証実験では、電子請求書の授受・管理を一元化することで、請求業務にかかる時間を平均約69%削減しました。
財務会計システムと連携すれば、支出命令書作成の半自動化も可能です。

理由2.DXの障壁(押印規則など)がなくなってきているから。

請求書DXを導入する効果は知っていても、押印規則などがDX化の障壁の1つとなっている自治体も多くありました。
M市(人口33万人)の事例を紹介します。M市では財務規則の見直しと文言の整理を行い、事業者へ「請求書の押印廃止のお知らせ」を発表しました。
取り組みの結果、M市は個人では補助金の請求などで押印省略の割合が高くなり、事業者でも工事の請求などで緩やかに押印省略の割合が増加しているとのこと。
こうした押印廃止の動きは、全国の自治体に広がりを見せています。
お知らせの内容
事業者が押印を省略する場合に必要な措置 ※一部抜粋
- ①請求書に住所・氏名等の必要事項に加え「発行責任者及び担当者」の氏名・連絡先(電話番号)を必ず記載すること。
- ②請求書に記載した連絡先(電話番号)に、M市から本人確認の連絡をする場合があること。
押印省略の効果
- 各種押印書類が同一印影であるかの確認作業が減少。
- 電子受領を可能としたことで、事業者側も移動や郵送などの物理的時間が短縮。
- 是正後の再提出なども短時間で対応可能となり、支払い遅延が抑制。
押印廃止に関するこちらの記事も参照ください。
番外編:事業者の法対応に貢献し、地域全体のデジタル化を図れるから。
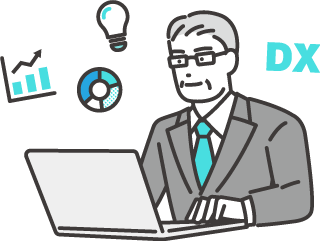
当社にお問合せいただく自治体の中には、「事業者から電子で帳票を発行したいという声を聞くが、どのように対応すれば良いか分からない」「対応できなかった場合、事業者のデジタル化の足かせになってしまうのではないか」という不安の声も聞かれます。
電子で発行された請求書(メールに添付されたPDFも対象)は、電子帳簿保存法に対応した保管が必要です。「改ざん防止の措置が取られている」真実性の確保と「検索や確認がすぐにできる」可視性の確保といった要件を満たさなければなりません。
双方がIDを持つプラットフォーム型で請求書を授受することで、全ての法対応をシステムベンダーが行うため、事業者は煩雑な法対応の負担なく、安心して電子取引が行えます。自治体が事業者の協力を得て、積極的に電子で請求書授受を行うことで、事業者間にも会計事務DXが波及し、地域全体の効率化と生産性の向上が図れます。
電子帳簿保存法第10条の法的要件を満たすサービスとして、JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)が認証する「電子取引ソフト法的要件認証制度」の第1号認証を取得しています。

こちらのニュースリリースもご参照ください。