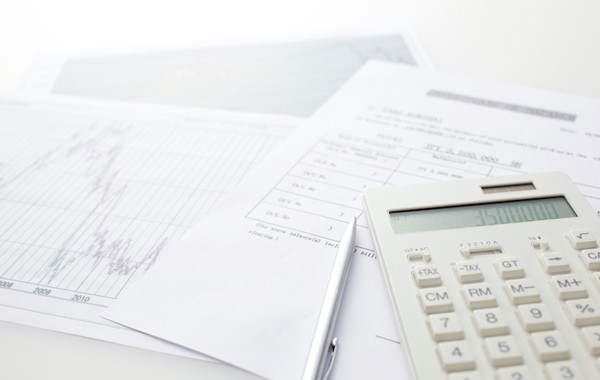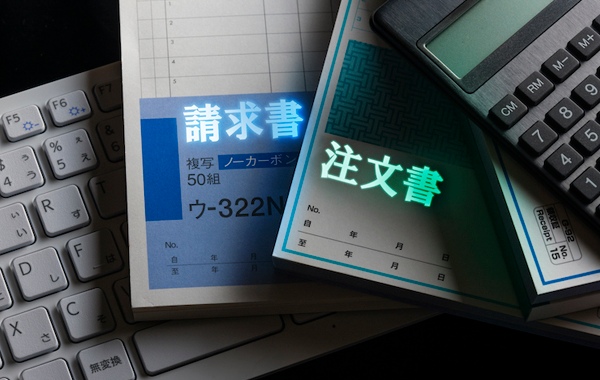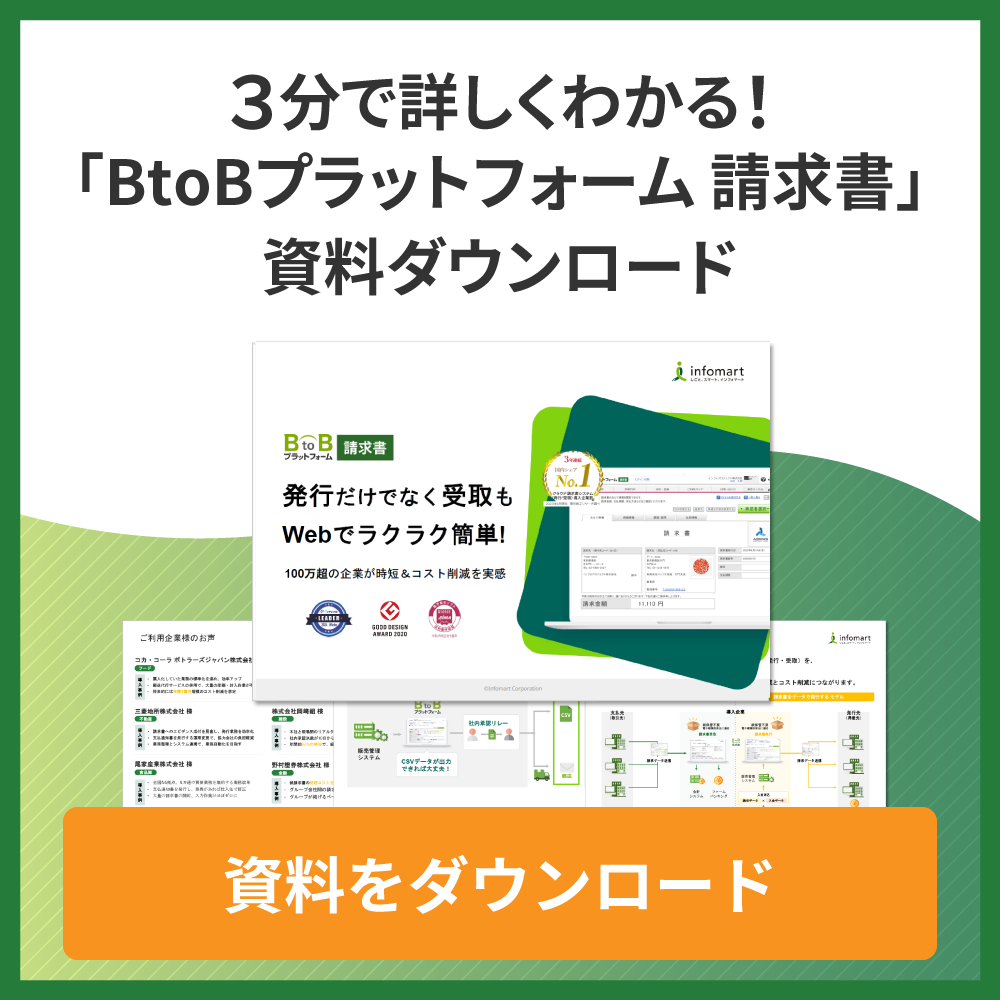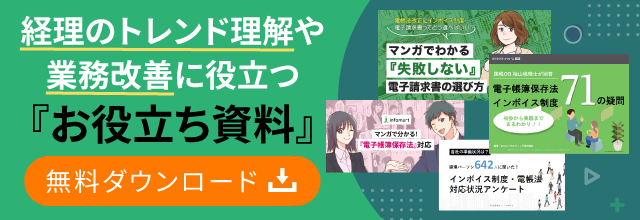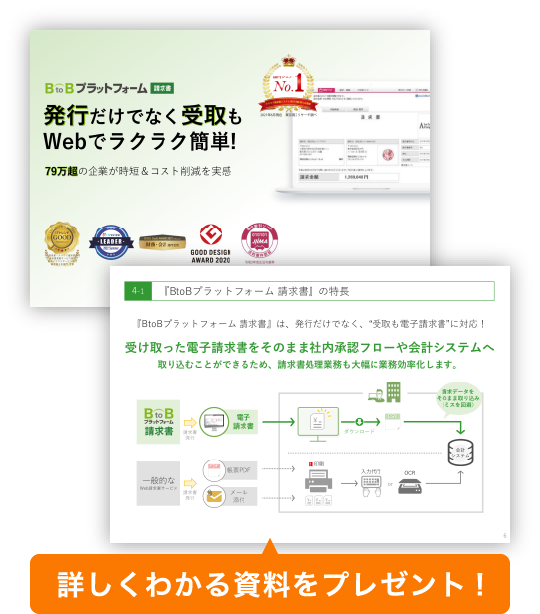最終更新日:2024年6月6日
目次
- 電子帳簿保存法とは、帳簿や書類を電子データで保存することを定めた法律
- 電子帳簿保存法の区分と要件
- 電子取引への対応が難しい場合の特別措置
- 電子帳簿保存法の改正で何が変わったの?
- 電子帳簿保存法に則った交付後の請求書控えの扱い方
- 請求書を電子データで交付した場合
- 請求書を紙で交付した場合
- 電子帳簿保存法に則った請求書を発行する場合の注意点
- 編集できない形式で発行する
- 電子取引で発行した請求書控えは電子データで保存する
- 改ざん防止のためにタイムスタンプを押す
- 検索できるようにする
- これまで紙で請求書を発行していた顧客、紙を希望する顧客へ説明する
- 請求書を電子請求書に切り替えるメリット
- 発行のコストを削減し、請求書の発行・発送処理を効率化できる
- 紙で保管する必要がなくなる
- セキュリティを強化できる
- テレワーク等の働き方改革を推進できる
- 人的ミスを防止できる
- 検索性が向上する
- 電子帳簿保存法に対応したシステムの導入を検討しよう
- よくある質問
- Q. 電子帳簿保存法で請求書の発行側に保管義務はありますか?
- Q. 電子帳簿保存法に請求書のタイムスタンプは必須ですか?
- Q. 電子データで請求書を受け取った側は印刷して保存しても問題ないですか?
電子帳簿保存法とは、帳簿や書類を電子データで保存することを定めた法律
電子帳簿保存法とは、国税に関係する帳簿や書類を電子データで保存することに関する法律で、保存した電子データの取扱方法などについても定めています。
電子帳簿保存法は、ほぼすべての事業者が対象で、企業の規模や法人か個人事業主かにかかわらず対応しなければなりません。
電子帳簿保存法の区分と要件
電子保存には、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引のデータ保存」の3つの区分があり、それぞれに保存要件が定められています。・電子帳簿等保存(任意)
電子帳簿等保存とは、会計ソフトや請求書発行システムなどで電子的に作成した国税関係の帳簿や書類を、電子データで保存することができるという保存区分です。国税庁により定められた「最低限の要件」と「優良な電子帳簿の要件」の2つの保存要件を満たす場合に、電子保存が可能となります。
なお、電子帳簿等保存は任意のため、紙で保存しても問題ありません。
・スキャナ保存(任意)
スキャナ保存は、紙で受け取った請求書や、紙で発行した請求書の控え、手作業で作成した国税関係の帳簿や書類などをスキャンし、電子データとして保存する区分です。電子帳簿等保存と同様に対応は任意のため、紙のまま保存することも可能です。
・電子取引(義務)
電子取引は、メールで受領した電子請求書や領収書、ウェブサイトからダウンロードした書類など、電子データで受け取った書類を電子データのまま保存する区分のことをいいます。
電子帳簿保存法改正により、2024年1月以降は義務化され、猶予措置の要件を満たさない限りは、例外は認められなくなりました。
電子取引のデータ保存においては、下記の要件を満たす必要があります。
<電子取引の保存要件>
・真実性の確保
・可視性の確保
この点については、次の項目で詳しく解説します。
※電子帳簿保存法の詳細については「電子帳簿保存法とは?対象書類と保存要件や期間をわかりやすく解説」をご覧ください。
電子取引への対応が難しい場合の特別措置
電子帳簿保存法改正により、2024年1月から電子取引を行ったデータの電子保存が義務化されました。これにより、ほぼすべての事業者が電子取引を行ったデータを電子保存しなければいけなくなりました。しかし、即時対応が難しい事業者に配慮し、国税庁は「猶予措置」を設けています。下記の条件すべてにあてはまる場合は、猶予措置が認められます。
<猶予措置の条件>
・保存要件に従って電子取引データを保存できないことについて、所轄の税務署に相当の理由があると認められた場合
・税務調査等の際に、要求されたデータのダウンロードや、書面での提示・提出の求めに応じられるようにしている場合
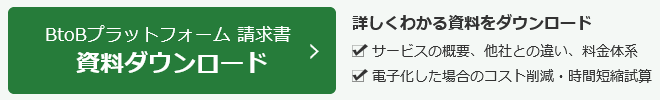
電子帳簿保存法の改正で何が変わったの?
電子帳簿保存法は1998年に施行され、その後複数回にわたって改正が行われてきました。直近では2022年に電子化を前進させるための大きな改正が行われています。この改正で電子取引における「紙の保存に代える措置」が廃止となり、電子取引した電子データは電子データのまま保存することが原則となりました。
その後、電子データ保存に対応するための準備期間として2年の宥恕措置が設けられた上、2024年1月に電子取引における電子データ保存が義務化されています。
電子取引における電子データは、単に電子データとして保存すれば良いわけではありません。電子取引のデータ保存の要件として定められている「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つの要件を満たして保存する必要があります。
それぞれの要件は下記のとおりです。

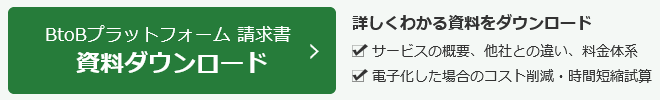
電子帳簿保存法に則った交付後の請求書控えの扱い方
前述したとおり、電子帳簿保存法は原則としてほぼすべての事業者が対象となるため、書類を受け取る側だけではなく、発行する側も同様の対応が求められます。
電子帳簿保存法の規程に即した、請求書控えの扱い方には大きく2パターンあります。
請求書を電子データで交付した場合
請求書を電子データで交付した場合は、電子帳簿保存法に則って、控えを電子データのまま保存する義務が発生します。
請求書の控えの保存期間は、法人の場合は原則として7年、個人事業主の場合は5年です。
また、2023年に開始したインボイス制度(適格請求書等保存方式)における適格請求書発行事業者は、適格請求書に含まれる書類を交付する際には、控えを作成して保存しなければなりません。保存期間は、適格請求書を交付した日が属する課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過した日を起点として7年間です。
請求書を紙で交付した場合
紙で交付した請求書については、電子データ保存の対象とならないため、控えも紙のまま保存して構いません。ただし、電子取引における電子保存の義務化を機に、請求書の電子化を進めたい場合などは、原本をスキャンして電子データに変換してから電子保存するといいでしょう。その際は、スキャナ保存の保存要件を満たしていることを確認してください。

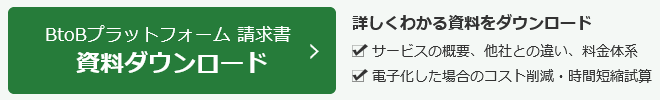
電子帳簿保存法に則った請求書を発行する場合の注意点

実際に請求書を電子取引する場合、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。ここでは、電子帳簿保存法に則った方法で請求書を発行する場合の注意点をご紹介します。
編集できない形式で発行する
請求書の電子データは、PDF形式などの編集できない形式で送付します。
作成した請求書を電子データで送るか紙で送るかは、顧客と合意の上で決定します。電子データで送ることが決まったら、WordやExcelといった編集可能な形式は避けて、PDF形式で送付しましょう。
電子取引で発行した請求書控えは電子データで保存する
電子請求書を発行した場合は、必ず電子データのままで保存しましょう。2024年1月の電子帳簿保存法改正により、電子請求書を発行した場合、控えも電子データで保存することが義務化されたからです。
改ざん防止のためにタイムスタンプを押す
電子請求書が改ざんされていないことを証明し、真実性の確保の要件を満たすために、タイムスタンプを押します。タイムスタンプは時刻認証業務認定事業者によって電子データに付与される「日付と時刻」のことで、タイムスタンプを付与した後に電子請求書をやりとりすることで、データの信頼性を担保することができます。
また、訂正や削除の記録を残したり、そもそも訂正や削除ができないようにしたりするシステムの導入も信頼性の向上につながるでしょう。
検索できるようにする
発行した電子請求書は、原則として「年月日」「金額」「顧客」の3項目で検索できるようにしておかなければなりません。ファイル名に上記の3項目を含めることで、検索性を高めて情報の可視化を図りましょう。
これまで紙で請求書を発行していた顧客、紙を希望する顧客へ説明する
電子帳簿保存法に則り、紙の請求書から電子請求書に変更する場合、これまで紙の請求書でやりとりしていた顧客に状況を説明して理解を求める必要があります。顧客によっては、請求書の電子化が難しい場合もあるため、必要に応じて対応ルールを設けるといいでしょう。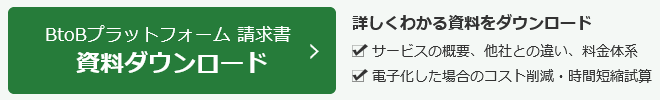
請求書を電子請求書に切り替えるメリット
電子請求書に切り替えることで、どのようなメリットがあるのでしょうか。電子請求書を発行する側にとって、メリットは下記の6つがあります。
発行のコストを削減し、請求書の発行・発送処理を効率化できる
紙の請求書を郵送する場合に比べて、電子請求書は発行にかかるコストを抑えられます。
2023年12月に総務省は、手紙とはがきの郵便料金を引き上げる案を諮問し、料金改定がある場合は、今以上に郵送にかかるコストが増えることが予想されます。
また、請求書管理ソフトで請求書を作成・印刷した後、宛名・金額・明細を販売管理ソフトの情報と照らし合わせ、封筒への印刷・封入・投函までを担う担当者の人的コストと時間的コストは甚大です。
請求書をメールで送ることによって、従来の作業を圧縮でき、請求書業務にかかるコストと負担の軽減が期待できます。それにより、請求書の発行・発送処理業務がシンプルになり、効率化できるのもメリットのひとつです。
紙で保管する必要がなくなる
電子帳簿保存法の要件にあった電子請求書の控えを作成すれば、紙で保存する必要はなくなります。顧客が多い企業では、バインダーや棚などを使って保管のスペースを確保する必要があり、オフィスのスペースを圧迫します。請求書には一定の保管期間が設けられているため、保管した請求書の管理にも手間がかかるでしょう。
電子請求書にすることで、オフィスの省スペース化と管理の省力化が実現します。
セキュリティを強化できる
紙の請求書に比べて、電子請求書はセキュリティ性能が高いです。紙の請求書には、火災による焼失や盗難、紛失などによる情報消失や情報漏洩のリスクがあります。電子請求書であれば、クラウド上で恒常的に保管できたり、ファイルにパスワードをかけたりすることで、安心して情報のやりとりが可能です。
テレワーク等の働き方改革を推進できる
テレワークなど、働き方改革を推進できるのも電子請求書のメリットです。紙の請求書がある限り、そのやりとりに関わる営業部門や経理部門は出社する必要があり、テレワークへの移行が困難だとされてきました。電子請求書への移行により、ネットワーク環境さえあれば請求書の発行・受け取り・管理が可能になるため、働く場所の制限が少なくなります。
人的ミスを防止できる
電子請求書は、ヒューマンエラーの防止にもつながります。手作業で請求書を作成・送付する場合、件数が増えるほど金額や宛先、明細などの誤記入や、封筒への入れ違いなどが起こる可能性があります。ミス防止のため、二重三重にチェックするための人件費や時間がかかるのも問題です。
電子請求書であれば、システムを利用して作成を自動化することができ、ヒューマンエラーの低減が叶います。
検索性が向上する
電子請求書は、先に挙げたとおり「年月日」「金額」「取引先」の3項目で検索できることが原則であり、システムを使って条件を設定するだけで簡単に目当ての請求書を探し出せます。紙の請求書の場合、該当する請求書がある棚から1枚の請求書を探し出すのはかなりの手間です。PDF化して保存した場合でも、フォルダから目的の請求書を見つけ出すまでには時間がかかるでしょう。
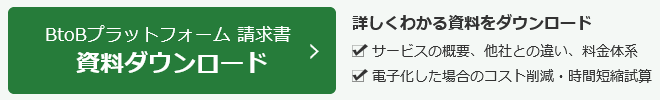
電子帳簿保存法に対応したシステムの導入を検討しよう

電子帳簿保存法によって、請求書発行側は業務の効率化やペーパーレス化の進展が期待できます。請求書発行をより安全に行いたい場合は、インボイス制度と電子帳簿保存法に対応したシステムの導入がおすすめです。
株式会社インフォマートでは、お客様の状況とニーズに合わせて導入できるシステムをご用意しています。
請求書の発行業務を電子帳簿保存法に則ってデジタル化したい場合は「BtoBプラットフォーム 請求書」がおすすめです。「BtoBプラットフォーム 請求書」は、請求書を電子データで発行するシステムで、システム自体が電子帳簿保存法に対応しているため、紙やPDFだとかかる保管コストや管理の手間も不要です。紙の請求書を必要とする顧客への郵送代行や、入金消込の自動化も可能なため、状況に合わせて無理なく電子化を進められるでしょう。また、取引先には無料でシステムを利用してもらえるのもメリットのひとつです。
業務フローを現在のままに、電子帳簿保存法対応を手軽に進めたい場合は「BP Storage」、発注段階から納品、請求業務までデジタル化したい場合は「BtoBプラットフォーム TRADE」がおすすめです。
電子取引データの電子保存の義務化を受けて、電子請求書への移行を考えている方は、必要に応じたシステムの導入をご検討ください。
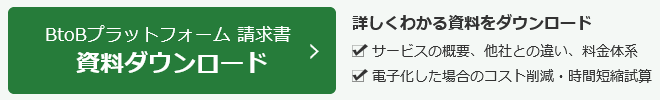
よくある質問
Q. 電子帳簿保存法で請求書の発行側に保管義務はありますか?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)における適格請求書発行事業者は、適格請求書に含まれる書類を交付する際には、控えを作成して保存しなければなりません。請求書をPDF化してメールで送った場合は、そのデータが控えに位置し、電子請求書システムで発行した場合は自動的に履歴が残り、そのデータが控えにあたります。詳しくは「電子帳簿保存法に則った交付後の請求書控えの扱い方」をご確認ください。
Q. 電子帳簿保存法に請求書のタイムスタンプは必須ですか?
電子データを訂正、修正、削除した履歴が残る、あるいは訂正、修正、削除等ができないシステムを使用している場合は、請求書へのタイムスタンプ付与は必須ではありません。Q. 電子データで請求書を受け取った側は印刷して保存しても問題ないですか?
2022年の改正電子帳簿保存法以降は、すべての事業者に電子でやりとりした取引データを電子データのまま保存することが義務化されました。ただし、2024年1月以降も猶予措置が設けられ、一定の要件を満たした事業者は保存義務を猶予されます。詳しくは「電子帳簿保存法におけるデータ保存はいつから?猶予措置とともに解説」の記事をご確認ください。
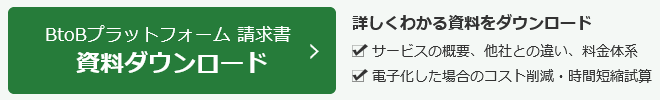
監修者プロフィール

宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。
【保有資格】CFP®、税理士